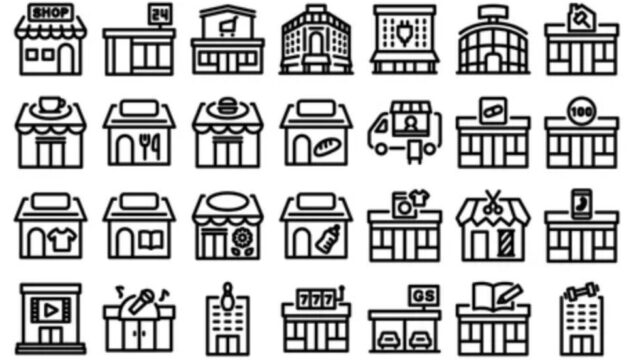1. フランチャイズとは?親会社・子会社との違いをまず理解しよう
フランチャイズという言葉を聞くと、多くの人が「コンビニ」や「学習塾」「飲食チェーン」などを思い浮かべるかもしれません。しかし、「親会社」「子会社」といったビジネス用語と混同している人も少なくありません。この記事では、まずフランチャイズの基本構造と、親会社・子会社との違いについて明確に解説します。
フランチャイズとは、事業の本部(フランチャイザー)が、ブランド名やビジネスモデル、運営ノウハウなどを提供し、加盟者(フランチャイジー)がその仕組みを活用して独立開業するビジネスモデルです。たとえば、セブンイレブンやローソン、明光義塾などが有名なフランチャイズ展開企業です。
一方で、親会社・子会社という関係は「資本関係」を指します。親会社は株式などを保有して他社をコントロールする立場にあり、子会社はその傘下で経営される会社のことです。つまり、親会社は経営上の意思決定を支配できるのに対し、フランチャイズ本部は加盟店に対して直接的な支配権は持ちません(契約に基づく運営ガイドラインはあるものの、経営者はあくまでフランチャイジー自身です)。
この違いは、開業する側にとって非常に重要です。親会社・子会社モデルでは雇われ社長や支社的な役割が強く、独立性が薄れる一方で、フランチャイズは「脱サラして独立したい」という方にとって自由度が高い選択肢になります。
こちらの記事では、さらに詳しくフランチャイズと法人関係の違いについて解説しています。
次に、直営チェーン店との違いについて詳しく見ていきましょう。
【大見出し2】
2. フランチャイズ本部と親会社の関係性を図解で解説
フランチャイズ本部と親会社の関係を理解することは、フランチャイズ加盟を検討するうえで非常に重要です。ここでは、代表的な構造と事例を交えて、わかりやすく解説していきます。
まず基本的なモデルとして、フランチャイズ本部が親会社の子会社として機能しているパターンがあります。例えば、大手学習塾の「明光義塾」は、親会社である株式会社明光ネットワークジャパンのフランチャイズブランドです。親会社がしっかりと経営基盤を支えており、FC本部はその事業部門や子会社として存在しているのです。
一方で、「餃子の王将」や「マクドナルド」などのように、フランチャイズ本部が親会社に直接属さずに、独立企業として存在しているケースもあります。この場合、本部自体が単独で事業展開しているため、経営上の自由度は高い反面、親会社による支援やバックアップが期待できない可能性もあります。
また、企業グループの中に複数のブランドが存在する場合、ひとつの親会社が複数のFC本部を傘下に持つこともあります。たとえば「ベネッセホールディングス」は、学習塾だけでなく、通信教育や介護事業など多岐にわたるフランチャイズ事業をグループ全体で展開しています。
こうした関係性を図解で理解しておくと、加盟前に「このフランチャイズの経営母体は信頼できるか?」「親会社がしっかりしているか?」を見極める目安になります。
こちらの記事では、フランチャイズ本部と親会社の資本関係を事例と共に紹介しています。必ず参考にしてください。
【大見出し3】
3. フランチャイズ業界で見られる「親会社と子会社」の構造実例
ここでは、学習塾・飲食・介護など各業界におけるフランチャイズ本部と親会社の関係性の具体的な実例をご紹介します。加盟を検討している方にとって、企業の実体を知ることは「失敗しない加盟」の第一歩です。
まず、学習塾業界の代表格である「明光義塾」。このブランドは株式会社明光ネットワークジャパンが運営するフランチャイズ型学習塾です。明光ネットワークジャパンは東証プライムに上場しており、親会社として安定した経営基盤を持っています。これにより、フランチャイズ加盟者は広告支援、教務研修、システム導入といった強力なバックアップを受けることができるのです。
次に、「ITTO個別指導学院」を展開する株式会社がんばる学園も、学習塾フランチャイズの中では有力な事例。こちらも親会社が経営支援を行い、全国にフランチャイズ展開しています。
飲食業界では、「からあげ縁(ゆかり)」を展開する株式会社ガネーシャが、親会社として「ワタミグループ」に属しています。親会社が持つ資本力とノウハウが、加盟店の成長を強力にサポートしており、飲食未経験者でも独立しやすい環境が整えられています。
介護業界では、「ツクイのデイサービス」などがフランチャイズ展開をしており、ツクイホールディングスが親会社としてインフラ整備や法的対応のサポートを提供しています。法改正の影響を受けやすい介護分野では、こうした親会社の存在がフランチャイズ加盟者の安心材料になります。
こちらの記事では、学習塾・介護・飲食などのフランチャイズの親会社構造と支援内容を詳細に解説しています。
このように、業界によってフランチャイズと親会社の関係性は様々。だからこそ、自分が加盟したい分野の構造を知ることが不可欠です。
【大見出し4】
4. フランチャイズとビジネスインキュベーションの違いとは?
近年、起業や独立を目指す人々の間で「フランチャイズ」と「ビジネスインキュベーション」が注目されています。どちらも「新規事業を始める支援」を目的としていますが、その構造や支援体制、メリットには明確な違いがあります。
まず、フランチャイズとは、すでに確立されたブランドやノウハウを本部から提供してもらい、その仕組みを用いて店舗運営を行うビジネスモデルです。たとえば、コンビニの「ファミリーマート」や学習塾の「個別教室のトライ」などが該当します。すでに成功しているビジネスモデルをそのまま使えるため、ゼロからの起業よりも失敗リスクが抑えられます。
一方、ビジネスインキュベーションとは、まだ立ち上がっていない、もしくは創業初期のスタートアップに対して、事務所の提供、アドバイス、資金支援などを行いながら育成する仕組みです。こちらは主に自治体・大学・民間団体などが支援機関となり、法人化前後の起業家を対象にするのが特徴です。
このように、フランチャイズは「既にある成功モデルを活用する独立」であり、ビジネスインキュベーションは「自らのアイデアをゼロから育てる創業支援」と位置づけることができます。
たとえば、「脱サラして手堅く開業したい」人にはフランチャイズが適しており、「自分だけのアイデアで勝負したい」人にはインキュベーション支援が向いています。
こちらの記事では、フランチャイズとインキュベーション支援の違いについてさらに詳しく解説しています。
「自分に合った独立の形はどちらか?」を見極めるためにも、それぞれの特徴とリスクを知っておくことが重要です。
【大見出し5】
5. フランチャイズ本部が倒産した場合、加盟店はどうなる?
フランチャイズビジネスにおいて、最も恐ろしいリスクのひとつが「フランチャイズ本部の倒産」です。加盟店が安定的に運営できていたとしても、本部が経営破綻した場合、その影響を大きく受ける可能性があります。
実際にあったケースとして、飲食業界で全国展開していた「とんかつ浜勝」のフランチャイズ本部が経営破綻し、多くの加盟店が独立再建を迫られた事例があります。このように、本部の経営が危うくなると、ロイヤリティの支払い先、仕入れルート、ブランド使用権などがすべて混乱します。
また、法的には本部が倒産してもフランチャイズ契約は即時消滅するわけではありません。しかし、ブランドの維持や運営支援が停止するため、実質的に加盟店側が営業不能になることもあります。さらに、本部が親会社の子会社である場合、親会社が連鎖倒産を防ぐために支援するケースもあれば、見捨てて撤退することもあります。
このようなリスクに備えるためには、加盟前に「本部の財務状況」「親会社の支援体制」などを調査しておくことが重要です。また、契約書には「本部倒産時の措置」などの項目が明記されているかも確認しましょう。
こちらの記事では、フランチャイズ倒産時の具体的な対応策や契約上のポイントについて詳しく説明しています。
独立開業は夢の実現でもありますが、こうした「もしも」に備えることが長期的な安定経営につながります。リスク回避のための情報収集を怠らないようにしましょう。
—
6. フランチャイズ契約と親会社との直接契約の違い
6-1. 加盟者視点で見る契約先の違いと責任範囲
フランチャイズビジネスにおいて「誰と契約するのか?」は非常に重要です。特に混同しやすいのが、フランチャイズ契約と親会社との直接契約との違い。たとえば、明光義塾に加盟する場合、契約相手は親会社である株式会社明光ネットワークジャパンではなく、FC本部として機能する関連会社や部門となります。
一方で、親会社と直接契約するケースは、たとえば直営店舗のオーナー業務を業務委託として受けるような形態であり、FCとは性質が異なります。フランチャイズ契約では、「独立した個人事業主や法人」として加盟し、商標・ノウハウ・マニュアルを借りる代わりに、ロイヤリティを支払う仕組みです。
責任範囲の違いも明確です。親会社と直接契約している場合、その親会社の指示命令や業務委託契約に従う必要がありますが、フランチャイズ契約では「独立性」が原則であり、契約上の責任もオーナー自身に帰属します。
6-2. トラブル時の対応力に差が出る理由とは?
契約主体がFC本部と親会社で異なると、トラブル発生時の対応にも差が出ます。FC契約では、「あくまで本部が契約主体」となっており、親会社は直接関与しないケースがほとんど。そのため、FC本部がトラブル対応に不慣れだったり、倒産した場合には、親会社が助けてくれる保証はありません。
しかし、親会社が直接契約に関与しているモデルでは、資本力や法務体制がしっかりしており、万が一の時の対応スピードやクレーム対応の手厚さに大きな差が出ます。特に大手企業が運営するフランチャイズでは、この「親会社のバックアップ体制」が安心材料となることも。
たとえば、セブン-イレブン・ジャパンのように、親会社(セブン&アイHD)のグループ企業として強い法務・財務体制を整えている企業は、加盟店からの信頼も厚く、契約に関するトラブルが起きた際の対応にも定評があります。
—
—
7. 学習塾フランチャイズに多い親会社主導型とは?
7-1. 教育業界での安定経営を支える親会社の存在
学習塾業界では、大手フランチャイズの多くが「親会社主導型」のビジネスモデルを採用しています。このモデルでは、親会社が経営戦略や資本を握り、フランチャイズ本部を支援・統制しているケースが一般的です。たとえば、「個別教室のトライ」は、株式会社トライグループが親会社として運営を支えています。また、「明光義塾」は、株式会社明光ネットワークジャパンという上場企業が親会社であり、資金力やブランド力を活かした戦略展開を行っています。
こうした親会社の存在は、フランチャイズオーナーにとって非常に大きな安心材料です。なぜなら、事業継続の基盤がしっかりしているため、景気後退期でも柔軟な経営支援が受けられる可能性が高まるからです。教室運営のノウハウ提供、教材開発、システム管理なども親会社主導で効率化されており、加盟者は現場業務に集中できます。
7-2. 塾業界でよくある子会社モデルの特徴と課題
一方、学習塾フランチャイズでは「子会社型モデル」も少なくありません。これは、親会社が子会社を通じてFC本部を運営し、その子会社が加盟店と契約する形式です。たとえば、「ITTO個別指導学院」は、株式会社やる気スイッチグループHDが親会社となり、関連会社を通じてブランド展開を行っています。
このような構造では、加盟者が契約を結ぶのは子会社であり、直接的には親会社との関わりはありません。しかし、実際の運営ノウハウや教材開発などは親会社主導で行われるため、一定の品質・水準は確保されています。ただし、FC本部(子会社)の判断によって支援の手厚さが変わる場合もあり、運営力の格差が出やすいのがデメリットです。
また、親会社からの資本依存が強すぎる場合、突然の方針転換(ブランド統合・撤退)などに巻き込まれるリスクもあります。そのため、加盟前には親会社・子会社の関係性と運営実績をよく調査する必要があります。
—
—
8. フランチャイズのメリットと親会社の関与による安心感
8-1. 親会社がいることで得られる「保証」と「サポート」
フランチャイズで独立・開業する最大の魅力のひとつが、「未経験からでも成功しやすい環境」が整っていることです。その環境をさらに支えるのが、親会社の存在です。たとえば、全国に店舗展開している「ナビ個別指導学院」は、親会社である株式会社ワオ・コーポレーションの強力な教育システムと広告支援体制を活かし、開業後も安定した集客と運営支援を受けられます。
親会社の関与があることで、開業初期の初期投資リスクや、運営中の販促負担、法務面の対応など、多方面にわたって手厚いサポートが提供されるケースが多くあります。特に教育業界のように、信頼と実績が求められる業種では「親会社のブランド力=顧客の安心感」に直結するため、開業直後でも比較的スムーズな集客が可能です。
8-2. 独立系フランチャイズとの違い・比較
一方で、親会社がいない独立系フランチャイズも数多く存在します。たとえば、創業者が1人で立ち上げたベンチャー型フランチャイズなどは、柔軟で革新的なビジネスモデルを持っていることもありますが、反面、資本力や経営基盤の安定性には不安が残ります。
親会社がバックにいるフランチャイズでは、事業資金の確保や危機管理能力に優れており、長期的なサポートを期待できます。これは開業後のトラブル対応や、加盟店同士の連携、経営判断のブレの少なさに大きく影響します。逆に独立系では、経営者の力量に事業全体が左右されやすく、成長スピードが速い反面、不安定な要素も含まれています。
したがって、自身がどのような独立スタイルを目指すのかによって、親会社の関与があるフランチャイズを選ぶか、独立系を選ぶかの判断が重要になります。安定・安心を求めるのであれば、資本力と実績を持つ親会社がいるフランチャイズがおすすめです。
—
—
9. 子会社型フランチャイズと直営型のメリット比較
9-1. 子会社型フランチャイズのスピード感と統制力
子会社型のフランチャイズでは、親会社が全体戦略を描き、その戦略に基づいて子会社がフランチャイズ展開を行います。たとえば「やる気スイッチグループ」が展開する「スクールIE」や「チャイルド・アイズ」は、親会社の明確なビジョンのもと、子会社が柔軟にFC展開を担っており、エリアごとのニーズに応じた出店が可能です。
このモデルのメリットは、決裁スピードと実行力の高さです。子会社はフランチャイズ部門に特化しており、経営判断や加盟店支援において迅速に動くことが可能。また、運営マニュアルや教育体制なども本部主導で一元化されており、加盟者にとっては迷いなくビジネスに集中できる環境が整っています。
さらに、親会社との資本的つながりがあるため、万が一の資金ショートやトラブル発生時にもリスクヘッジが効きやすい点も魅力です。結果として、全国規模での多店舗展開も実現しやすい構造になっています。
9-2. 直営モデルの限界とFC展開の優位性
一方で、直営型ビジネスモデルは「全てを本部で管理する」スタイルです。たとえば、かつての「栄光ゼミナール」などがそうで、教室数を一定規模まで増やすことはできますが、すべてを本部が管理するため、資本や人材、マネジメントの限界がすぐに訪れます。
この点、フランチャイズはオーナーが自分の責任で運営するため、人的リソースを効率的に活用でき、結果として出店スピードが格段に上がります。FCオーナーが現地の事情に通じていることで、地域密着型の経営も実現しやすく、直営モデルに比べて柔軟性に優れているのもポイントです。
ただし、加盟者の質が成果に直結するため、教育やマネジメント体制が脆弱だとブランド毀損リスクも生じやすくなります。つまり、直営とFCは一長一短であり、親会社の力を活かした子会社型フランチャイズは、その中間をうまく補完するハイブリッドな選択肢とも言えるでしょう。
—
—
10. フランチャイズ失敗事例に見る「親会社不在のリスク」
10-1. FC本部が倒産して加盟店が孤立したケース
フランチャイズビジネスの失敗は、個人オーナーだけでなく本部側にも起こり得るものです。特に親会社を持たないFC本部の場合、資金繰りの悪化や経営ミスによって倒産するケースも少なくありません。たとえば、2010年代に一部で展開されていた地方発の小規模学習塾フランチャイズでは、本部のノウハウや集客支援体制が脆弱だったことにより、オーナーが赤字経営を強いられ、最終的には本部の倒産に至ったケースがあります。
こうした事例では、本部が倒産した瞬間に加盟店との契約は宙に浮き、ロイヤリティ支払い義務はなくなるものの、ブランド使用も禁じられ、運営継続に大きな支障が出ます。マニュアル、システム、教材なども使用できなくなることが多く、「いきなり無保険状態」に放り出されることになります。
このように、親会社のいない独立型FC本部では、倒産時に支援もなく、オーナーが最もリスクを背負う立場となります。
10-2. 親会社による救済が機能した成功事例も紹介
一方で、親会社の存在がフランチャイズ加盟者を守った成功事例もあります。たとえば、学習塾フランチャイズ「森塾」は、親会社である株式会社スプリックスの支援体制が整っており、コロナ禍における急激な環境変化にも柔軟に対応。教室ごとの個別支援策や教材無償提供など、親会社の資金力と機動力を活かしたサポートを実施し、加盟教室の大半が継続できました。
また、飲食系フランチャイズでも、「ほっともっと」などを展開する株式会社プレナスは、本部の収益が悪化しても親会社が全体を下支えする構造を持ち、加盟店の雇用・運営を最優先で守る姿勢を貫いています。こうした事例を見ると、親会社の存在は単なる資本力の担保ではなく、危機時に「背中を押してくれる存在」として加盟者に安心感を与えていると言えるでしょう。
FC加盟を検討する際には、本部単体の魅力だけでなく、「その裏にどんな親会社がいるのか」まで含めて調べることが、成功の鍵になります。
—

11. 親会社の「資本力」と「ブランド力」が与える影響
11-1. 加盟者から見たブランド信頼性と安心感
フランチャイズビジネスにおいて、親会社の存在がもたらす「ブランド信頼性」は、加盟希望者にとって非常に重要な判断材料となります。特に塾や飲食、介護など、消費者との接点が密接な業種においては、ブランドの知名度とイメージがそのまま売上や集客力に直結します。
たとえば、【明光義塾】の親会社は東証スタンダード市場に上場している「株式会社明光ネットワークジャパン」です。このように上場企業が親会社として運営しているケースでは、経営基盤の安定性やガバナンス体制が強く、加盟者としても「このフランチャイズなら信頼できる」と感じやすいのが特徴です。
また、ブランドイメージがすでに確立していることで、開業時から一定の集客が見込めるという点も魅力のひとつです。知名度のあるフランチャイズでは広告費のコスト削減も期待できます。
11-2. 資金支援・広告支援など親会社ならではの強み
親会社がしっかりとした資本力を持っている場合、加盟店に対する「初期投資支援」や「キャンペーン費用の一部負担」など、さまざまな経営サポートが得られます。たとえば、大手飲食チェーンの【スシロー】は、親会社「FOOD & LIFE COMPANIES」の強力な資本力を背景に、店舗展開のスピードや広告出稿量を圧倒的に確保しています。
このように、資金面やマーケティングの支援体制が充実していると、フランチャイズ加盟者が本業に集中しやすくなり、売上を安定化させる近道になります。また、親会社が広告の全国展開を担うことで、地域に限らず集客効果が最大化されるのも大きなメリットです。
—

12. フランチャイズにおける法的トラブルと責任の所在
12-1. 親会社は責任を負うのか?契約条項に注意
フランチャイズ契約における法的トラブルは、実は多くの人が誤解しているリスクの一つです。特に「親会社がフランチャイズ本部を運営している=親会社がすべて責任を取ってくれる」と思い込んでしまうケースは非常に多いのですが、これは危険な誤解です。
基本的に、フランチャイズ契約はFC本部と加盟者との間に締結されます。仮にその本部が親会社の子会社であっても、**親会社は契約の当事者ではありません**。つまり、法的責任は直接負わないのが原則です。
たとえば、介護業界で急成長していたフランチャイズ【カイポケ介護サービス】では、加盟者が「親会社の保証があるもの」と誤認し、後に本部の対応不備でトラブルに発展した例もあります。契約書にはっきり「親会社は契約の当事者でない旨」が記載されていることも多く、加盟前に必ず確認すべきポイントです。
12-2. 加盟前にチェックすべき契約書のポイント
法的トラブルを未然に防ぐためには、契約書の読み込みが何より重要です。特に次のような条項に注目してください:
– 親会社と本部の関係性の明記
– トラブル発生時の解決手段(裁判/仲裁/協議)
– ロイヤリティ算出方法と支払い義務
– 本部倒産時の契約の取扱い
これらを確認せずに署名してしまうと、後になって想定外の費用負担を求められたり、サポートが得られなかったりするケースも少なくありません。
また、信頼できる弁護士に「契約書レビュー」を依頼するのも有効です。契約のリスクを事前に把握しておくことで、トラブル回避につながります。
—

13. FC本部・親会社・加盟店の三者関係を理解しよう
13-1. トップダウン型とボトムアップ型の運営構造
フランチャイズビジネスにおいては、「親会社」「FC本部」「加盟店」という三者の関係性を正しく理解することが非常に重要です。この構造がどう設計されているかによって、運営方針、裁量の自由度、支援内容などが大きく異なってきます。
一般的に、親会社→本部→加盟店というトップダウン型が多く見られます。これは親会社が大きな資本と経営方針を持ち、FC本部はその実行部隊として機能、加盟店はその指示や支援のもとで運営を行うという構造です。たとえば【マクドナルド】は、日本マクドナルド株式会社がFC本部であり、その親会社である米国マクドナルドがグローバル戦略を握っています。
一方で、加盟店の意見を汲み取りながら本部の方針を柔軟に調整するボトムアップ型の運営を採用するチェーンもあります。教育業界の【ITTO個別指導学院】などは、オーナー会の意見を反映しやすい体制を構築しています。
13-2. 各立場が果たす役割と成功の条件
三者の関係性を明確にしておくことで、スムーズな運営と長期的成功につながります。以下のような役割を各立場が担っています:
– 親会社:全体戦略・資本支援・ブランディング
– FC本部:日常オペレーション管理・マニュアル提供・教育研修
– 加盟店:現場運営・顧客対応・地域密着の実行
このバランスが崩れると、「本部が支援してくれない」「親会社の指示が一方的」「加盟店が本部を無視」など、トラブルの原因になります。成功しているフランチャイズは、三者間の信頼関係と役割分担が明確で、継続的なコミュニケーションが取れているという共通点があります。
—

14. フランチャイズ加盟前に調べておきたい「経営母体」
14-1. FC本部の資本関係・親会社情報を確認する方法
フランチャイズ加盟を検討する際、最も重要なチェックポイントのひとつが「経営母体=親会社の存在と状況」です。見落としがちですが、実はこの部分が加盟後の安定性に直結します。
調べ方としては、まず「会社概要」や「IR情報」「商業登記簿謄本」を確認します。上場企業であれば、親会社と子会社の関係は開示義務があり、簡単にチェック可能です。たとえば、【やる気スイッチグループ】が展開する「スクールIE」は、持株会社「やる気スイッチグループホールディングス」が経営母体です。
一方で、非上場の本部や独立系FCの場合は、親会社情報の開示が不十分なケースも。その場合は「帝国データバンク」「東京商工リサーチ」などの企業情報データベースを使うのも有効です。
14-2. 経営状態の見極め方と注意すべき赤信号
経営母体を調べる際には、単に「親会社があるかどうか」だけでなく、**その経営状態や収益性にも目を向けるべきです**。特に以下のような項目に注意しましょう:
– 売上・利益が3期連続で減少していないか
– 負債比率が高すぎないか
– 代表者が頻繁に変わっていないか
– 監査法人が急に変更されていないか
こうした兆候が見られる場合、将来的にFC本部のサポート体制が弱くなったり、最悪の場合倒産リスクが高まったりする可能性があります。実際に、かつて人気を集めた飲食フランチャイズの【カレーうどん千吉】は、親会社の経営不振が原因でサポートが激減し、加盟者離れが起きたと報じられました。
—

15. 親会社と良好な関係を築くための加盟戦略
15-1. フランチャイズ説明会で聞くべき「親会社との関係」
フランチャイズ説明会に参加する際、多くの方が「事業モデル」や「収益性」ばかりに注目しがちですが、実はそれ以上に重要なのが「親会社と本部の関係性」を明確に把握することです。
たとえば、親会社が経営にどれだけ関与しているのか、事業方針の決定は親会社主導なのか本部独自なのかを確認することは、長期的な運営方針の安定性に直結します。実際に、【個別指導Axis】を展開するワオ・コーポレーションのように、親会社が教育コンテンツやシステム面まで支援しているケースでは、オーナーとしても安心して事業に専念できます。
質問例としては、
– 「本部と親会社の資本関係はどうなっていますか?」
– 「過去に親会社変更や経営統合などの事例はありますか?」
– 「親会社が関与しているサポート体制の内容は?」
などを聞いてみると、曖昧な答えを返す本部より、信頼できる本部かどうかが見えてきます。
15-2. 契約後も関係性を保つためのコミュニケーション術
契約後、オーナーと本部の関係性は「受け身」ではなく、積極的に築いていくべきものです。親会社が運営に関与しているフランチャイズでは、**オーナーの声が親会社の方針に反映されることもある**ため、定期的な報告・相談・意見交換は欠かせません。
たとえば、飲食業界の大手フランチャイズ【餃子の王将】では、オーナーが参加する定例会議やアンケートの意見を基に、新しい商品開発やキャンペーンが組まれています。こうした双方向の関係性は、ブランドの成長と加盟店の満足度向上に繋がります。
メールだけでなく、対面の交流会や個別相談の場を積極的に活用し、親会社・本部との信頼関係を築いていくことが、長期的な成功への鍵です。
—