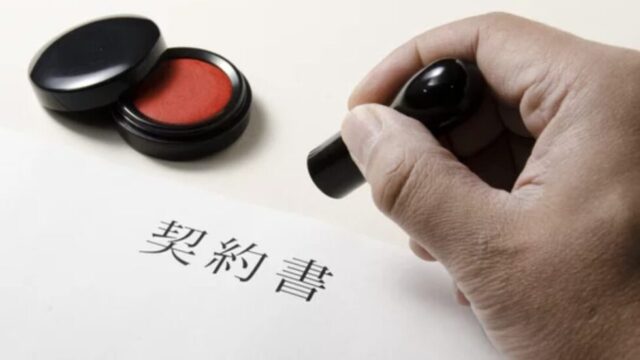1. フランチャイズとは?基本の仕組みをわかりやすく解説
フランチャイズとは、あるビジネスモデルやブランド、商品・サービスの提供方法を確立した本部(フランチャイザー)が、そのノウハウを加盟者(フランチャイジー)に提供し、対価として加盟金やロイヤリティを受け取る仕組みです。加盟者はそのブランド力や仕組みを活用することで、比較的スムーズに開業・運営が可能となります。
たとえば、全国展開している学習塾「明光義塾」や「個別教室のトライ」、飲食業で有名な「からやま」や「銀だこ」なども、実はフランチャイズ展開をしており、各店舗の多くは個人や法人のオーナーが経営しています。これらは本部が確立したブランドイメージや運営ノウハウを活かして、地域に根ざした店舗展開ができるのが大きな特徴です。
フランチャイズの仕組みは、基本的に以下のような要素で構成されています。
本部と加盟者の役割分担
本部はブランドの使用許可、業務マニュアル、研修制度、商品供給、販促支援などを提供します。一方、加盟者はそのブランドを使用して店舗を運営し、売上の一定割合や定額のロイヤリティを本部に支払います。
この関係性があることで、未経験の業種でも開業・運営が可能になり、初期の失敗リスクを抑えることができます。ただし、マニュアル通りに運営する必要があり、独自の工夫がしづらいという一面もあります。
フランチャイズビジネスの拡大理由
現在、多くの企業がフランチャイズ展開を積極的に進めています。その背景には、店舗拡大のスピードを加速させられる点、初期費用を本部がすべて負担しなくて済む点、そして地域特性を理解したオーナーが事業を展開することで集客力が向上するという利点があります。
特に教育業界では、人口減少が進む中でも「個別指導塾」や「幼児教育」に特化したフランチャイズが安定したニーズを誇っています。「やる気スイッチグループ」や「英会話のGaba」などは、そのブランド力とサポート体制が評価され、多くのオーナーに選ばれています。
こちらでフランチャイズの基本についてさらに詳しく解説しています。
—
2. フランチャイズ経営者に求められる資質とは?
フランチャイズでの独立や脱サラを目指すにあたり、まず考えるべきは「自分が経営者としてやっていけるか」という点です。フランチャイズは本部のサポートが充実しているとはいえ、最終的に責任を負うのは加盟店オーナー自身。つまり、経営者としての適性や資質が大きく問われるビジネスモデルだといえます。
実際に、フランチャイズ経営で成功する人には共通する特徴があります。それは「素直さ」「実行力」「人との調和性」の3つです。本部のマニュアルや指導を素直に受け入れられる柔軟さを持ちつつ、それを即座に実行に移せる行動力が重要です。また、スタッフや地域の顧客と良好な関係を築けるコミュニケーション力も欠かせません。
特に、学習塾のフランチャイズにおいては、保護者や生徒との信頼関係が集客と継続率に直結します。「スクールIE」や「ナビ個別指導学院」など、教育サービスを提供する業態では、経営者が教育に対して一定の理解や関心を持っていることも成功の要因になります。
経営は「人間力」が試される
経営者に求められるのは、会計知識や戦略だけではありません。現場を回し、スタッフを育て、売上を作るというサイクルの中で「人を動かす力」が何よりも必要です。多くのフランチャイズ本部では、開業前に経営者研修を実施しており、たとえば「からあげの天才」や「コメダ珈琲店」では、店舗オペレーションや数値管理を含めた長期研修を用意しています。
経営初心者でも成功できる理由
意外にも、経営初心者のほうがフランチャイズで成功しやすいという話もあります。なぜなら、過去のやり方にこだわらず、本部の指導を素直に実行しやすいからです。「未経験から開業3年で年商1億円を達成」という事例も、「まいどおおきに食堂」や「銀のさら」などで報告されています。
こちらで、フランチャイズ経営者に向いている人の特徴をさらに詳しく紹介しています。
—
3. フランチャイズと直営店の違いをビジネス構造で比較
フランチャイズと直営店は、どちらも同じブランド名で運営される店舗形態ですが、ビジネス構造はまったく異なります。ここを理解せずにフランチャイズ加盟してしまうと、「思っていたのと違う…」と後悔するリスクがあるため、独立を検討する段階で明確に把握しておくことが重要です。
直営店とは、企業が自ら資金を出して、運営も直接行っている店舗です。たとえば「スターバックス」や「無印良品」は、基本的に直営モデルでの展開を主軸としています。これに対して、フランチャイズ店は、ブランド使用料や契約金を支払った加盟者が運営主体となり、本部が間接的に店舗を拡大していく仕組みです。
オーナーの立場・利益構造の違い
直営店では、本社がすべての売上・コスト・人材をコントロールできますが、店舗拡大には多大な資金と人員を要します。一方、フランチャイズは、本部がリスクを分散でき、オーナーが地域に根ざして責任を持って店舗運営するため、現場力が高くなる傾向があります。
利益の面では、直営店はすべての収益が本社に入るのに対し、フランチャイズではオーナーが売上からロイヤリティを差し引いた額を利益として受け取ります。たとえば「銀だこ」では、売上の10%前後が本部へのロイヤリティとされており、それ以外はオーナーの裁量で管理する形です。
意思決定の自由度と支援体制の違い
直営店は本部の管理下にあり、意思決定も一貫していますが、フランチャイズ店では一定の自主性が求められます。ただし、自由度には限りがあり、販促方法や仕入れ先などは本部指定となることがほとんどです。
一方、支援体制という点では、フランチャイズ本部は開業前研修や人材教育、販促支援などを通じて、オーナーの立ち上げ・運営をバックアップしています。特に「トライプラス」や「ペッピーキッズクラブ」などの教育業態では、教室マネジメントから教材提供まで一貫したサポート体制が評価されています。
こちらで、フランチャイズと直営店のビジネスモデルの違いをより詳しく確認できます。
—
4. 塾・学習塾のフランチャイズとは?特徴とメリット
塾・学習塾業界は、フランチャイズモデルが非常に盛んな分野のひとつです。少子化が進む中でも「教育にお金をかける家庭」は一定数存在しており、安定したニーズがある市場といえるでしょう。特に、個別指導や英会話などのニッチ分野に特化したフランチャイズは、差別化しやすく、地域性を活かした展開も可能です。
たとえば「明光義塾」や「ナビ個別指導学院」、「スクールIE」などは、個別指導に特化したフランチャイズで、未経験者でも始めやすい体制が整っています。これらのブランドは全国に教室を展開しており、本部からの教材提供やカリキュラム指導、研修制度などが充実しているのが特徴です。
塾フランチャイズの強みとは?
第一に、教育ニーズの安定性が挙げられます。景気に左右されにくく、「子どもには良い教育を」という親の思いが強いため、一定の集客が期待できるのです。特に小中学生を対象にした個別指導塾は、学区ごとの生徒数や地域の進学実績に影響されにくく、地方都市でも十分に成り立ちます。
第二に、在庫リスクが少ないという点。飲食業のように食材の仕入れが不要で、運営コストが比較的低いため、利益率も高めです。実際に「やる気スイッチグループ」や「トライプラス」では、加盟者の平均利益率が20~30%を超えるケースもあると言われています。
本部サポートが成功のカギ
学習塾フランチャイズでは、本部の支援体制が非常に重要です。生徒募集のノウハウ、講師採用の仕組み、授業の品質管理、保護者対応など、多くの業務をサポートしてくれる本部であれば、初心者でも安心して始められます。
「ペッピーキッズクラブ」のような英語教室型フランチャイズでは、外国人講師の手配やレッスンのカリキュラムまで本部が提供してくれるため、英語が話せないオーナーでも運営可能です。また、「チャイルド・アイズ」など、幼児教育に特化したモデルも注目されています。
こちらで、学習塾フランチャイズの特徴や成功のポイントをさらに詳しくご紹介しています。
—
5. フランチャイズの経営のみを任せられるモデルとは?
フランチャイズと聞くと「自分が現場に立って運営する」というイメージを持たれがちですが、実際には“経営のみ”に専念できるフランチャイズモデルも増えています。これは「現場はスタッフに任せて、自分はオーナーとして戦略や数値管理に集中する」という形で、複数店舗展開を目指す方や、他事業と並行したい人にとって非常に魅力的な選択肢です。
たとえば、個別指導塾の「トライプラス」や「スクールIE」では、教室の運営を教室長や講師に任せつつ、オーナーは経営数値の把握や定期的な方針決定に集中できます。同様に、車のリペアサービス「トータルリペア」も、スタッフに技術面を任せながら、経営者として集客や売上戦略を担うモデルです。
経営に特化するメリットと注意点
経営専任型フランチャイズの最大のメリットは、「時間の融通がききやすく、他の事業や本業と並行しやすい」ことにあります。副業として始める方、脱サラ後の資産運用として考える方には特に向いています。
一方で、信頼できる現場責任者を確保できなければ、店舗の運営品質が落ちたり、スタッフの離職に繋がったりするリスクもあります。実際、経営者が現場に無関心すぎて、売上が低迷した事例も少なくありません。フランチャイズ本部が提供する「現場代行プログラム」や「人材紹介制度」をうまく活用することが成功のカギです。
どんな業種が経営特化に向いているか?
経営のみで成り立ちやすい業種には、以下のような傾向があります:
– オペレーションが標準化されている(マニュアルが明確)
– 人材の採用・教育支援が本部に整っている
– 自動化やオンライン化が進んでいる
この点で注目されているのが「ファディー(FURDI)」という女性専用AIフィットネスジムです。スタッフ常駐が不要で、会員がICカードで入室・トレーニングを行う無人型モデルのため、経営者は在庫・人件費・労働時間の面でも優れた効率性を得られます。
こちらで、経営に専念できるフランチャイズモデルについてより詳しく確認いただけます。
—
6. 初心者におすすめのフランチャイズ業種とは?
これからフランチャイズに加盟しようと考えている初心者の方にとって、最も重要なのは「失敗しにくい業種を選ぶこと」です。特に脱サラ後の独立や副業でのチャレンジであれば、なるべくリスクを抑え、安定収益を確保できるモデルが理想です。
まず初心者におすすめされるのは、**運営マニュアルが整備されており、本部サポートが手厚い業種**です。たとえば、清掃や修理など専門知識が不要な「リペア・サービス系」、オペレーションが簡素な「無人店舗・省人化型業種」、そして地域密着で始めやすい「学習塾・教育系」がその代表です。
教育・飲食・サービス業の比較
フランチャイズにはさまざまな業種がありますが、初心者が検討すべきは以下の3つです:
– **教育業(例:明光義塾、トライプラス、スクールIE)**
→ 在庫不要、収益構造が安定、ブランド力による集客力が魅力。学歴や教員免許は不要でOK。
– **飲食業(例:からやま、コメダ珈琲、銀だこ)**
→ 高収益が期待できる一方で、初期費用が高め。人材管理や衛生管理のノウハウが必要。
– **サービス業(例:トータルリペア、ファディー、おそうじ本舗)**
→ 技術職ながら、本部研修で習得可能。1人でも始められるモデルが多く、固定費が安く済む。
中でも「ファディー(FURDI)」は、女性専用AIフィットネスジムとして急成長中の無人型モデルで、店舗にスタッフを常駐させずとも運営が可能です。これは初心者にとって非常に大きな魅力です。
初心者向けチェックリスト:この条件を満たせば安心
以下のチェックポイントを満たすかどうかで、初心者向きか否かを判断できます:
– 本部の支援体制が充実している
– 集客サポート(広告・HP・SNS)が整っている
– 契約期間に縛りが少なく、途中解約時のペナルティが小さい
– 1人でも開業できる or 最少人数で運営できる
– 成功事例・失敗事例が公式に公開されている
こちらで、初心者におすすめのフランチャイズを一覧で比較できます。
—
7. フランチャイズ経営のメリット5選
フランチャイズで独立や脱サラを目指す方がまず注目すべきは、「なぜフランチャイズが選ばれるのか」という点です。起業には多くのリスクが伴いますが、フランチャイズモデルにはそれを軽減する**独自のメリット**があります。ここでは、フランチャイズ経営における代表的な5つの利点を紹介します。
①ブランド力を活用できる
もっとも大きな魅力は、やはり**既に認知されているブランド名の力**です。たとえば「コメダ珈琲」や「からやま」、「銀だこ」などは、開業初日から集客力があり、広告費や販促の手間が少なく済むのが特徴です。
ブランドの信用力があることで、立ち上げ当初から顧客が来店しやすく、リピートにもつながります。これは個人経営の新規開業ではなかなか得られないアドバンテージです。
②ノウハウと支援体制が整っている
フランチャイズ本部から提供されるノウハウや運営マニュアルは、**過去の成功・失敗から導き出された黄金ルール**です。これを活用することで、初心者でも経営が軌道に乗りやすくなります。
たとえば「おそうじ本舗」では、技術研修に加えて集客のノウハウ、顧客対応のマナー研修も充実しており、経験ゼロからでも始められるよう設計されています。
③資金調達や融資の通りやすさ
実は、フランチャイズは金融機関からの融資が受けやすいという側面もあります。「実績あるブランド」と「運営実績をもつ本部のサポート」があることで、信用力が高まり、融資審査の通過率が上がるのです。
特に「明光義塾」や「トライプラス」のように全国展開している教育系FCは、地域金融機関との相性もよく、事業計画書のテンプレートも本部が提供しています。
④短期間での事業立ち上げが可能
個人開業では開店準備だけで数カ月〜半年以上かかることが一般的ですが、フランチャイズでは**本部が立地選定・内装施工・設備発注などを一括サポート**してくれるため、早ければ2〜3カ月で開業可能です。
さらに、オープンイベントの運営やチラシ配布なども本部で代行可能なケースもあり、スムーズにスタートダッシュを切ることができます。
⑤孤独な経営にならない
個人事業主にありがちな悩みが「孤独感」ですが、フランチャイズでは常に本部がパートナーとして伴走してくれるため、安心感があります。また、同じフランチャイズオーナー同士の横のつながりもできやすく、成功事例や改善ポイントの共有も可能です。
こちらで、フランチャイズ経営のメリットについてより詳しくご覧いただけます。
—
8. フランチャイズのデメリットとその乗り越え方
どんなに魅力的なフランチャイズでも、メリットだけでなくデメリットも存在します。成功するためには、**これらの弱点を事前に理解し、対処方法を知っておくことが極めて重要**です。このセクションでは、フランチャイズにおける代表的なデメリットと、それらにどう向き合うべきかを詳しく解説します。
①ロイヤリティや初期費用が重くのしかかる
フランチャイズ加盟時には、ブランド利用料や研修費、店舗準備費用など、**初期費用が数百万円単位でかかること**が一般的です。さらに月額ロイヤリティが発生し、売上の数%〜固定費として本部へ支払う必要があります。
この点については、事前に損益シミュレーションをしっかり行い、**ロイヤリティ比率が低めなフランチャイズを選ぶ**ことが対策となります。たとえば「トータルリペア」は月額固定制で、売上が多くてもロイヤリティは一定。経営の見通しが立てやすいのが特長です。
②経営の自由度が制限される
フランチャイズでは、本部が定めた運営マニュアルや商品ラインナップに従う必要があり、**自分のアイデアを活かしにくい側面**があります。たとえば、メニュー変更や広告表現、価格設定などを自由に変更できないこともあります。
この点を乗り越えるには、**契約前に「どこまで自由に裁量を持てるか」を確認すること**が大切です。柔軟性のあるフランチャイズ本部も増えており、特に新興ブランドほど加盟店に裁量を与える傾向があります。
③本部との関係悪化リスク
一部のフランチャイズでは、本部からのサポート不足や契約トラブル、ロイヤリティの未説明などが発生し、**本部とオーナーとの信頼関係が壊れる**ケースも見受けられます。これが経営に大きく影響することも。
契約時に必ず「加盟店契約書」を第三者の法律専門家に確認してもらい、**不明点はすべて質問してクリアにしておく**ことが最善の予防策です。
④閉店・撤退時の制限がある
思うように売上が伸びず、撤退したいと考えても、契約期間中の解約には違約金が発生することがあります。また、閉店後も一定期間、同じ業種で開業ができない「競業避止義務」が設けられているケースもあります。
このため、**契約期間・解約条件・競業避止義務の有無**について、加盟前に確認することが必須です。
こちらで、フランチャイズ契約における注意点やデメリット対策を詳しく解説しています。
—
9. 実際にあったフランチャイズ経営の失敗事例
フランチャイズ開業は確かに魅力的ですが、**必ずしも全員が成功するわけではない**のが現実です。ここでは、実際にあった失敗例を紹介しながら、「なぜ失敗したのか?」「どうすれば防げたのか?」という視点で考察していきます。事前にリスクを知っておくことで、同じ轍を踏まない準備ができます。
①飲食系:仕入れ・人件費の管理ミスで赤字転落
ある脱サラ男性が「からやま」のフランチャイズに加盟し、開業直後は順調に見えました。しかし、スタッフの採用コストがかさみ、シフト管理もうまくいかず、**人件費が売上の40%を超えてしまった**ことから、収益が圧迫される結果に。加えて、近隣に競合の唐揚げ専門店が出店し、客足も減少。
→対策:**運営の自動化・シフト最適化・競合調査の徹底**が必要。また、飲食は原価と人件費のバランス管理が肝です。
②教育系:本部とのミスマッチによる閉業
「トライプラス」に加盟したある女性オーナーは、教育業への情熱が強かったものの、**本部の運営方針と自身の指導スタイルにズレ**を感じて不満が蓄積。最終的に契約を更新せずに撤退する事態となりました。
→対策:加盟前に必ず**本部の教育方針や理念を確認し、自分と合うかどうかを見極める**必要があります。
③サービス系:立地ミスで集客できず失敗
「おそうじ本舗」に加盟したオーナーは、住宅密集地から離れた工業地帯で出店。結果として、**主要ターゲットである主婦層からの依頼がほぼゼロ**で、3カ月で黒字化できず、半年後に撤退しました。
→対策:**立地選びは本部任せにせず、自分でも綿密にリサーチを行う**べきです。ターゲット層が明確な業種ほど立地が命。
④契約条件の見落としによる損失
あるオーナーは契約期間5年を「解約自由」と勘違いし、2年で撤退。しかし、契約書には違約金の明記があり、**撤退時に100万円以上のペナルティを負担**する羽目に。
→対策:**契約書を第三者(弁護士など)と一緒に確認する**ことが絶対です。曖昧な理解は大きな損失につながります。
こちらでは、失敗しないフランチャイズ選びのポイントを詳しく解説しています。
—
10. フランチャイズ契約で押さえるべき法律知識
フランチャイズ経営において見落とされがちなのが、「契約内容に関する法律知識」です。契約書にサインするということは、数年にわたって法的な拘束力を持つビジネス関係に入るということ。ここでは、加盟前に知っておくべき法律的ポイントやトラブル防止策をわかりやすく解説します。
①契約期間・中途解約・違約金の確認は必須
フランチャイズ契約では、**一般的に3〜10年ほどの契約期間**が設けられます。この期間中の中途解約には、高額な違約金が発生するケースが多く、注意が必要です。
たとえば、「5年契約・中途解約時は残存期間のロイヤリティ全額支払い」といった条項がある場合、2年で辞めても3年分のロイヤリティを支払う必要が出てくることも。
また、「競業避止義務」といって、**退会後に同業種で一定期間開業できないルール**も盛り込まれていることがあります。これに違反すれば、損害賠償請求されるリスクも。
→対策:契約期間・更新条件・中途解約の扱い・競業禁止の有無をすべて明確にチェックしましょう。
②情報開示義務と説明責任を果たさない本部に注意
フランチャイズ本部には、加盟希望者に対して**重要事項説明書の交付義務(中小小売商業振興法に基づく)**があります。この書面には、収支モデルやトラブル実績、直近の解約件数など、事業の健全性に関する情報が記載されているはずです。
もしこれらの開示を拒否する本部がいたら要注意。**「契約書だけで判断してはいけない」**のはこのためです。説明を受けずに契約し、後から「こんなはずじゃなかった」と後悔するケースは後を絶ちません。
→対策:重要事項説明書は必ず事前に読み込み、不明点は納得いくまで質問を繰り返してください。
③契約解除と裁判リスクも想定しておく
実際に起こった事例として、オーナーが「収支構造が聞いていた内容と異なる」として契約解除を求めたものの、本部は「説明義務を果たした」として対立。最終的に裁判に発展し、オーナー側が敗訴した例もあります。
こうした法的トラブルを防ぐには、契約書だけでなく、**商標の使用条件・損害賠償条項・契約解除時の手続き**までチェックすることが重要です。
こちらで、フランチャイズ契約書の確認ポイントを詳しく解説しています。
—
—
11. 経営のみで利益が出るモデルの選び方
人材と業務体制が整った「経営委託型フランチャイズ」を選ぶ
フランチャイズビジネスの中には、「自ら現場に立たずに経営のみで利益を上げられるモデル」も存在します。こうしたスタイルを希望する方におすすめなのが、「経営委託型フランチャイズ」です。このモデルは、現場業務をフランチャイズ本部または提携業者に委託し、オーナー自身は経営管理や収益確認、戦略的判断に専念できる点が大きなメリットです。
たとえば、家事代行業の大手「CaSy(カジー)」では、オーナーが実務に関わらなくても、本部が登録スタッフのマッチングや品質管理を代行してくれる仕組みを導入しています。ほかにも、店舗運営をすべて本部が代行し、オーナーは投資家としての役割に集中できる「完全委託型」もあり、これらは副業や多店舗展開を検討する方に特に向いています。
こちらで、経営のみのフランチャイズモデルの種類とその仕組みを詳しく解説しています。
「店舗運営の完全外注」には注意点も
ただし、「経営のみ」を目指すにはいくつかの注意点があります。まず、運営代行にかかるコストは安くありません。本部の運営手数料や人件費、品質管理費などが利益率を圧迫するケースもあるため、契約時には収支計画の細部までしっかり確認することが重要です。
また、ブランドによっては「一定期間の現場経験」が加盟条件として設けられている場合もあります。たとえば「ほっともっと」や「からやま」などの飲食フランチャイズは、一定期間のOJTが必須で、その後に経営委託へ移行できるパターンが多く見られます。
さらに、外注化によってサービスの品質が低下し、クレームや悪評につながるリスクも無視できません。経営者としては、委託先の教育・品質体制を十分に把握し、定期的にモニタリングや改善指示を行う責任があります。
こちらで、経営委託型フランチャイズの成功事例と失敗事例が紹介されています。ぜひ参考にしてください。
—
—
12. 初期費用が少ないフランチャイズ一覧
自己資金50万円以下から始められる低資金フランチャイズ
フランチャイズ開業というと「資金がかかる」イメージがありますが、実は初期費用を抑えてスタートできる業種やブランドも多く存在します。とくに注目したいのが、モバイル型・訪問型・無店舗型のビジネスです。
たとえば、スマホ修理やパソコン修理で全国展開している「スマホステーション」は、店舗不要で、カバン1つで出張修理ができるため、加盟金50万円以内でも開業可能です。また、家庭教師フランチャイズ「トライプラス」も、教室を本部が用意してくれるタイプの契約があり、自己資金30万円から開業できるプランも用意されています。
さらに、リペア業の「トータルリペア」は、工具一式がレンタルでき、月額サブスク型の支払いで徐々に設備を揃えていけるため、初期投資リスクを抑えながら開業できます。
こちらで、少資金で始められるフランチャイズ一覧を詳しく紹介しています。
初期費用が少ない=リスクが少ないとは限らない
初期費用が少ないフランチャイズには、当然ながらメリットもあればデメリットもあります。低資金で開業できるということは、設備や人員、集客インフラも最低限ということになりがちです。そのため、営業力やマーケティング力をオーナー自身が担う必要が出てくるケースも少なくありません。
たとえば、訪問型の「ベビーシッターサービス」や「ペットシッター」などは、開業資金こそ抑えられますが、リピーターを獲得するまでに時間がかかるため、短期的な利益が出にくい傾向があります。
また、フランチャイズ本部のサポート体制が十分でない場合、営業・契約管理・顧客対応までオーナーがすべて担うことになり、ワンオペ状態に陥るリスクもあります。契約前には必ず本部のサポート内容や収支モデルを確認しましょう。
こちらにて、初期費用別にフランチャイズを比較した記事をご覧いただけます。
—
—
13. 地域性を踏まえた業種選定のポイント
フランチャイズは地域の人口・ニーズに合わせて選ぶ
フランチャイズ経営で見落としがちなポイントのひとつが「地域性」です。同じ業種でも、立地や地域特性によって売上や集客力は大きく変わってきます。たとえば、都市部ではランチタイムの回転率がカギとなる飲食系、地方では送迎サービス付きの学習塾や訪問型ビジネスが有利に働く傾向があります。
具体的には、都市部では「銀のさら」や「串カツ田中」など、高いブランド認知と短時間での回転率を強みとする業種が人気です。一方、郊外や地方では、「ヒーローズ(HERO’S)」のように1対1指導を基本とし、地域の保護者ニーズに寄り添った学習塾が支持を得ています。
また、高齢化が進んでいるエリアでは、介護・リハビリ系フランチャイズ「レコードブック」などが地域住民から重宝されることもあります。
こちらで、地域密着型フランチャイズの選び方と成功のポイントを解説しています。
地元商圏調査はFC本部任せにせず自分でも行う
本部が提供する商圏調査レポートは、あくまでも「全体傾向」を示したもので、開業候補地の詳細な生活者ニーズまでは反映されていないこともあります。そのため、自分でも「駅周辺の人通り」「近隣に競合があるか」「地元住民の年齢層や所得層」といった情報を独自に調査することが重要です。
また、「地域密着」をうたうフランチャイズでも、実際には本部が積極的に地域イベントや行政連携に関与していないケースもあります。地域住民との関係づくりや口コミ誘導は、オーナーの努力に左右される部分が大きいため、自ら地域に足を運び、日常的な関わりを持てる姿勢も求められます。
こちらにて、地域に合った業種選びの実践例が紹介されています。
—
—
14. 副業として始められるフランチャイズの実態
本業を続けながら始められる「週末起業型フランチャイズ」
「脱サラはまだ不安」「本業を辞めずに副業から始めたい」——そんな人に人気なのが「週末起業型」または「副業OK型」のフランチャイズモデルです。これは、オーナーが現場に常駐せず、限られた時間で収益を生む仕組みが設計されたFCで、初期費用・稼働時間ともに抑えられるのが特徴です。
たとえば、「開運堂」や「ちょいCam」などは、週末だけ出張で販売活動を行うビジネスモデルで、倉庫や店舗を持たずに自宅を拠点にできます。また、「Total Repair(トータルリペア)」は車の内装修理を行う移動型ビジネスで、平日夜間や土日中心に稼働可能なため、副業利用の実績も多くあります。
こちらで、副業対応フランチャイズの具体例を紹介しています。
副業として成功するために必要な条件とは?
ただし、副業でフランチャイズを始める場合は、「自分がすべてをやろうとしない」ことが成功の鍵です。業務を委託したり、アルバイトやパートを雇用して、限られた時間で効率的に収益を上げる必要があります。また、週末だけで顧客を確保するには、Web集客やSNS運用などのスキルも求められます。
「副業OK」と謳っているブランドでも、実際にはオーナーの積極的な営業活動や顧客管理が必要なケースもあります。そのため、開業前には「週末だけで回る業務フローか?」「本部のサポートはどこまで受けられるか?」などを細かく確認しましょう。
なお、会社勤めをしながら副業FCを行う場合、就業規則の副業禁止条項には十分に注意してください。
こちらに、副業として成功したフランチャイズオーナーの体験談が掲載されています。
—
—
15. フランチャイズ本部のサポート内容を比較
本部サポートの範囲はブランドによって全く異なる
フランチャイズ加盟において「本部のサポート体制」は最重要項目の一つです。同じ業種でも、ブランドによってサポート内容・範囲には大きな違いがあり、それが経営の成功率を左右します。
たとえば、学習塾フランチャイズである「個別指導Axis」や「明光義塾」は、初期研修はもちろん、教室運営マニュアル、講師採用支援、シーズンごとのカリキュラム提供まで手厚いサポートがあります。一方、サポートが最小限で「自走力」が求められるモデルもあり、完全未経験者にとってはハードルが高いこともあります。
飲食系では「からやま」や「コメダ珈琲」などが、店舗立地調査から施工、スタッフ採用、開業後の巡回指導までを網羅しており、初心者でも安心してスタートできます。
こちらで、本部サポートの比較と体験談をまとめた記事をご覧いただけます。
研修制度・サポート内容の「中身」を事前に必ず確認する
「研修あり」「開業支援あり」といった表現は多くのフランチャイズで見られますが、その中身には注意が必要です。1日〜2日の形式的な研修で済まされるケースもあれば、2〜3週間かけて現場研修を行い、接客や経営管理を徹底指導する本部もあります。
また、開業後の支援として、定期巡回・経営相談・売上改善のコンサルを提供するところもあれば、マニュアル提供のみで終わるブランドもあります。特に「広告宣伝サポート」や「人材採用支援」が含まれているかどうかは、立ち上げ直後の集客力に大きく影響します。
加えて、問い合わせ対応やクレーム処理まで本部が代行してくれるモデルもあり、オーナーが業務に集中しやすい環境が整っています。
こちらで、研修・サポートの実態と加盟前に聞くべき質問リストをまとめています。
—