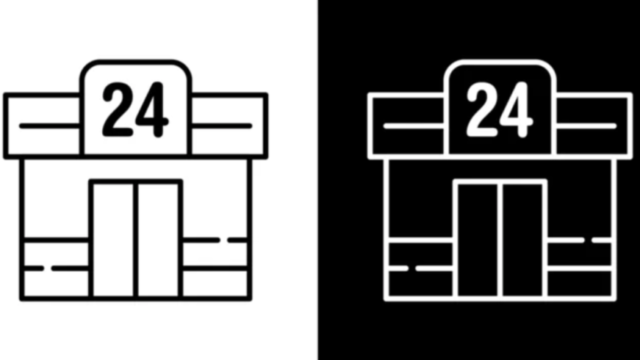1. フランチャイズとは?基本構造と業態別の仕組み
フランチャイズとは、ブランド力やノウハウを持つ本部(フランチャイザー)が、加盟店(フランチャイジー)に対して営業権や商標、ノウハウなどを提供し、対価としてロイヤリティや加盟金を受け取るビジネスモデルのことです。この仕組みにより、脱サラを考える個人や未経験者でも、比較的リスクを抑えて独立開業できる環境が整っています。特に飲食業界、なかでもラーメン店業態は、安定した需要と再現性の高いオペレーションから、フランチャイズ展開における王道業種とも言えます。
例えば、「一蘭」や「丸源ラーメン」などは直営中心ですが、「ラー麺ずんどう屋」や「ラーメン山岡家」などは積極的にフランチャイズ展開を行っており、未経験でも本格的なラーメン店を開業できるとして人気です。これらのブランドでは、セントラルキッチンからのスープ供給や専用の研修制度があり、運営のハードルを大きく下げています。
また、チェーン店とフランチャイズ店の違いも押さえておきましょう。チェーン店は本部が店舗運営も直轄で行う直営モデルであるのに対し、フランチャイズ店はオーナーが独立して経営します。つまり、フランチャイズには独立性がありながらも本部の支援が受けられるという点で、将来性を感じやすいモデルなのです。
フランチャイズ契約には、商標使用許諾、商品・サービスの提供、経営指導などの内容が盛り込まれます。本部と加盟者の間に明確な責任分担があることが、スムーズな多店舗展開を可能にしているのです。
こちらの記事では、フランチャイズのビジネス構造についてさらに詳しく解説しています。
このように、フランチャイズは本部と加盟店が協力し合う「共創型」のビジネスであり、脱サラで独立したい方にとっては非常に魅力的な選択肢となり得ます。ラーメン業界のように一定の業態特性を持つ分野では、特に成功しやすい土壌が整っていると言えるでしょう。
2. ラーメン業界でフランチャイズ展開が進む理由
ラーメン業界は、他の飲食業態と比べてフランチャイズ展開が進みやすい特徴をいくつも持っています。その一つが「商品構成の単純さと再現性の高さ」です。基本的にラーメンは、スープ・麺・トッピングという限られた構成で成立するため、標準化・マニュアル化がしやすく、フランチャイズにおいて必要な再現性を担保しやすい業態なのです。
加えて、ラーメン業態は日本人の食文化に深く根付いていることから、立地や時期に左右されにくく、安定した集客が見込めます。実際に「博多一風堂」「天下一品」「幸楽苑」といった有名ブランドが全国展開していることからもわかるように、開業や多店舗展開の将来性が期待されています。
中でも「ラーメン山岡家」は、東日本を中心にフランチャイズ展開を加速させている好例です。24時間営業の店舗スタイルや独自開発のスープ製造設備を導入することで、オペレーションを標準化し、加盟希望者の多様なニーズに対応しています。こうした工夫が「脱サラして独立したい」と考える方々にとって、大きな安心材料となっています。
また、ラーメンはテイクアウトやデリバリーとの親和性も高く、コロナ禍を経て市場適応力のある業態として再注目されています。このような市場動向も、フランチャイズ本部がラーメン業態を軸に展開していく追い風となっています。
こちらの記事では、ラーメン業界のフランチャイズ本部の戦略についてさらに詳しく解説しています。
フランチャイズでのラーメン屋開業は、固定ファン層の存在・高い利益率・ローコスト出店が可能など、独立や脱サラを考える個人にとって魅力的な選択肢です。今後もこの傾向は強まり、多くのブランドが加盟募集に力を入れていくと見られます。
3. フランチャイズ本部を立ち上げるための全体像
フランチャイズ本部を立ち上げるには、事前に明確なビジネス戦略と仕組み化が求められます。まず、現在運営している直営店がある場合は、その実績を基に「成功パターン」を洗い出し、再現可能な運営モデルとして体系化することが第一歩となります。そこから、商品・オペレーション・教育・ブランディングなどを整備していくことが、フランチャイズ化の土台となります。
ステップとしては、①ビジネスモデルの見える化 → ②加盟店サポート体制の構築 → ③契約書・ガイドライン作成 → ④加盟店の募集開始、という流れが一般的です。ここで重要なのが、初期のモデル店(直営)でしっかりと利益が出ているかどうか。利益が不安定な状態でフランチャイズ展開に進むと、加盟者にも損害を与えてしまうリスクがあり、本部の信頼性が損なわれます。
たとえば「ラーメンまこと屋」は、関西圏での直営展開を経て、成功モデルを磨き上げたのちにフランチャイズ募集を開始し、全国的な拡大に成功しました。開業資金のモデルや研修制度を整えたことにより、未経験者でも独立しやすい環境を提供し、多くの脱サラ希望者から支持を集めています。
本部立ち上げには、コンサルタントの力を借りるのも一つの手です。第三者視点でビジネスモデルを分析し、必要な資料や契約書の作成支援、サポート体制構築などをサポートしてくれる存在は、フランチャイズ本部の立ち上げにおいて大きな助けになります。
こちらの記事では、本部構築に必要なステップをさらに詳しく解説しています。
独立から本部立ち上げへ。これは簡単ではない挑戦ですが、将来的に多店舗展開を視野に入れているならば、避けては通れない道です。成功の鍵は「仕組み化」と「他者が運用できるかどうか」にかかっています。
4. フランチャイズに必要なマニュアルと運営体制の作り方
フランチャイズ展開において、マニュアルと運営体制の整備は成功可否を左右する極めて重要な要素です。なぜなら、加盟店オーナーの多くは業界未経験者であり、「誰がやっても再現できる仕組み」がなければ、安定した営業を継続するのは困難だからです。特にラーメン業態は職人技が必要というイメージが強いため、その「属人性の排除」がフランチャイズ化の第一歩となります。
まず作成すべきは「業務マニュアル」です。これには以下の3つが基本になります。
接客マニュアル(挨拶、レジ操作、クレーム対応)
調理マニュアル(スープの温度、麺の茹で時間、盛り付け)
衛生・安全管理マニュアル(清掃手順、消毒・保存管理)
これらのマニュアルは紙ベースだけでなく、動画教材やチェックリスト形式での提供も効果的です。たとえば「どうとんぼり神座(かむくら)」では、店舗オペレーションを徹底的にマニュアル化しており、独立希望の加盟者でも即戦力として現場に立てる仕組みがあります。
また、教育体制の整備も欠かせません。開業前研修、開業直後の立ち上げサポート、開業後の定期指導の3段階が基本です。ここで役立つのが、直営店で培ったノウハウや人材の活用です。現場経験豊富な店長クラスを開業支援チームとして派遣することで、現場とのギャップを埋められます。
さらに本部体制としては、スーパーバイザー(SV)の配置も必要です。SVは、店舗運営の相談窓口として、問題発生時の一次対応、業績向上支援、クレーム対応などを担います。将来的に多店舗展開を見据えるなら、このSV体制の整備は必須です。
こちらの記事では、開業準備とマニュアル整備の重要性について詳しく解説しています。
フランチャイズ本部としての将来性は、この「マニュアル」と「体制」に集約されるといっても過言ではありません。脱サラ希望者でも安心して加盟できる仕組みこそが、本部の価値そのものです。
5. 加盟店募集の仕組みと営業戦略とは?
フランチャイズ本部を立ち上げた後に直面する大きな課題のひとつが「どうやって加盟店を集めるか」です。加盟者の確保ができなければ、いくら事業モデルが優れていても多店舗展開は実現しません。特にラーメン業態は競合が多く、脱サラ希望者や独立志望者に対する魅力的な訴求が不可欠です。
まず、加盟店募集において重要なのが「明確なUSP(独自の強み)」の提示です。たとえば「一風堂」は、“世界基準の味”を前面に出し、海外展開実績まで加味したブランディングで加盟希望者を惹きつけています。また、「来来亭」では、未経験からの独立支援体制を強調し、脱サラ層に強くアプローチしています。
具体的な営業戦略としては、以下の手法が効果的です。
1. オウンドメディア・WEB集客
近年は「フランチャイズ 加盟 募集」などのキーワードで検索してくる見込み層が多く、情報提供型コンテンツ(ブログ・YouTube・説明会動画など)の整備が必須です。SEOやSNS広告の活用も、信頼性を高めるための重要な手段です。
2. フランチャイズ展示会・業界メディア掲載
「フランチャイズ・ショー」などの展示会出展は、対面での情報提供やリアルな信頼構築ができる場です。ここでは“実績”と“数字”が加盟希望者の判断材料になるため、明確な開業事例や収支モデルの開示が求められます。
3. 紹介制度・エージェント連携
既存加盟者からの紹介や、フランチャイズ紹介会社との連携も有効です。紹介報酬制度を設けることで自然な拡大が見込めます。
たとえば「伝丸」では、ラーメン業態で初期投資を抑えたプランと手厚い立ち上げ支援をPRポイントに掲げ、WEBと展示会の両軸で加盟開拓を進めています。こうした戦略を本部として設計することで、信頼と興味を得る導線ができていきます。
こちらでは、フランチャイズ加盟募集の進め方を詳しく紹介しています。
加盟者の多くは「将来性のある本部かどうか」「サポート体制があるか」「資金的に無理がないか」といった視点で見ています。それらをクリアに示し、“この本部なら大丈夫そうだ”という安心感を与えることが、成功のカギになります。
6. フランチャイズ立ち上げ時の資金と収益モデル
フランチャイズ本部を立ち上げる際には、しっかりとした資金計画と収益モデルの構築が不可欠です。本部は加盟店からロイヤリティや加盟金を受け取ることで収益を得ますが、それまでには教育体制やマニュアルの整備、契約書の作成、初期サポート要員の確保、マーケティングコストなど多くの初期投資が必要になります。
本部側で必要となる主な初期費用は以下の通りです。
コンサルタントへの依頼費用(数十万円〜)
契約書類やガイドライン作成費用
加盟店研修用のマニュアル・教材制作費
加盟募集のための広告・展示会出展費用
スーパーバイザーなど人件費の先行投資
これらを合わせると、本部側は数百万円からの資金準備が必要になるケースが多く、資金調達方法も計画的に進める必要があります。場合によっては、日本政策金融公庫の創業融資やベンチャー支援制度の活用も視野に入れると良いでしょう。
また、収益モデルにおいては「加盟金+ロイヤリティ」が本部の主な収入源です。たとえば「一風堂」などは加盟金300万円前後、月額ロイヤリティは売上の3〜5%という水準です。一方、「日高屋」のようにロイヤリティを廃止し、その代わり仕入れマージンで利益を得る形式を取っているブランドもあります。
このように、収益モデルは事業の方向性やブランドの性質によって柔軟に設計されます。加盟者の参入障壁を下げる「低加盟金+売上連動ロイヤリティ」のモデルは、脱サラ希望者に人気があります。実際に「丸源ラーメン」は初期費用のハードルを下げることで、多くの独立志望者の参入を実現しています。
こちらの記事では、フランチャイズ本部の資金モデルについて具体的に解説しています。
本部が収益を安定して得るためには、加盟者がしっかりと利益を出せるモデルになっていることが大前提です。加盟者の成功なくして、本部の成長はありえません。この視点を忘れずに、長期的なビジネススキームを組み立てましょう。
—
7. フランチャイズ契約書の基本構成と注意点
7-1. 契約書に盛り込むべき主要項目とは?
フランチャイズ本部を立ち上げる際、もっとも重要なのが「フランチャイズ契約書」の作成です。これは、加盟者との間で取り決める“約束ごと”であり、ビジネスの根幹をなす法的な文書です。
具体的には、次のような項目が必ず含まれます。
– ロイヤリティや加盟金などの費用体系
– 商標やブランドの使用に関するライセンス条項
– 営業地域や出店制限に関する取り決め
– 本部からのサポート内容
– 契約期間とその更新ルール
– 契約違反や解除の条件
たとえば、ラーメンフランチャイズで全国展開を果たした「一蘭」は、ブランド保護を徹底しており、類似メニューや類似サービスの展開は禁止されています。契約書に明確なガイドラインがあることで、ブランドイメージの毀損を防ぐことができるのです。
こちらでフランチャイズ契約の基本構成を詳しく解説しています。
7-2. 損害賠償や違約金などトラブル回避のための文言
契約書には、トラブル発生時の責任範囲を定めた「損害賠償条項」や「違約金規定」を明記することが重要です。たとえば、加盟店が本部のマニュアルに従わず独自のサービス展開を行い、事故やクレームが発生した場合の責任の所在を事前に明文化しておくことで、裁判や訴訟のリスクを大幅に軽減できます。
また、最近は「SNS炎上」などの予期せぬトラブルにも備え、ネット上での言動ルールや情報漏えいへの対応も盛り込む企業が増えています。ブランドの将来性を守るという意味でも、リスクマネジメントに関する条文の整備は不可欠です。
さらに、契約違反時に加盟者が支払うべき違約金の設定も透明にしておくことで、無責任な撤退を防ぐ抑止力となります。たとえば「ラーメン山岡家」では、退店時に清掃費や看板撤去費が別途発生する旨を明記し、費用のトラブルを最小限に抑えています。
—
8. フランチャイズ本部の責任と立場を理解する
8-1. 加盟店との信頼関係を築くための心得
フランチャイズ本部にとって、加盟店との関係構築はビジネス成功の要です。立ち上げ初期は契約面にばかり目が行きがちですが、「長期的な信頼関係こそが収益性を高める」と理解しておくべきです。
実際、成功しているラーメンフランチャイズ本部の多くは、教育支援・マーケティング支援・運営相談といった“人に寄り添うサポート”に力を入れています。たとえば、「天下一品」では、定期的にオーナー同士の意見交換会を開き、現場の声を本部が吸い上げる場を設けています。こうした場を通じて、加盟店が孤立しない仕組みを整えているのです。
本部と加盟店の関係性は、パートナーシップです。契約で縛るのではなく、伴走者として支える姿勢が、結果的に脱退率の低下とブランド強化につながります。
こちらでは、加盟店との信頼関係の構築術を紹介しています。
8-2. 契約上の責任・支援義務・ガバナンスの考え方
フランチャイズ本部には、「商標の貸与」や「ノウハウの提供」だけでなく、“加盟店の健全運営を支援する義務”があります。これを怠ると、契約不履行や損害賠償の対象になる場合もあるため、注意が必要です。
ガバナンスの視点で見ると、各店舗のクオリティを保つために定期監査やミステリーショッパー制度を設けることも重要です。「ラーメン魁力屋」では、ブランドイメージを維持するため、年に数回の全店舗チェックを行い、改善点をフィードバックしています。
また、原材料の統一や衛生基準の順守なども本部の責任領域です。店舗オーナーがそれぞれ異なる仕入れ先を使い、味や品質にばらつきが出れば、ブランド全体の信用が損なわれます。
フランチャイズビジネスは「共創」であり、本部の姿勢ひとつで加盟者の満足度と継続率が大きく左右されます。
—
9. フランチャイズ展開で失敗しないためのリスク対策
9-1. よくある失敗事例とその原因分析
フランチャイズ立ち上げは、将来性が高い一方で、失敗リスクも伴います。たとえば、ラーメンフランチャイズでは「運営オペレーションの不備」「収益モデルの見誤り」「加盟者へのサポート不足」が、代表的な失敗原因とされています。
具体的には、「とんこつラーメン専門店 風風ラーメン」が急拡大後に本部の管理体制が追いつかず、加盟者離脱が相次いだ過去があります。このように、勢いだけで多店舗展開を行った結果、教育不足や味のクオリティ低下を招き、結果としてブランド価値の毀損につながるケースが少なくありません。
他にも、契約トラブルや法的責任の所在が曖昧なまま加盟を進めてしまったために、後々の解約・訴訟問題へと発展した事例も見られます。
9-2. フランチャイズ崩壊を防ぐ事前チェックリスト
フランチャイズ本部として失敗を回避するためには、立ち上げ前に以下のような項目をチェックしておく必要があります:
– オペレーションマニュアルの完成度
– 商品力・ブランド力の市場評価
– 加盟店との収益分配バランス
– サポート体制の整備レベル
– 契約書に明記すべきリスク回避項目の確認
– 事業計画に対する現実的な収益シミュレーション
また、開業後も定期的なフィードバック制度の導入や、経営数字の共有・改善指導を通じて、加盟店とのズレを最小限にとどめることが大切です。
こちらで、フランチャイズ失敗例を踏まえた立ち上げ前の注意点を解説しています。
リスクの芽は初期段階から生まれます。それを“見逃さない設計”が、継続的なフランチャイズ成功の鍵を握っています。
—
10. ラーメンフランチャイズ成功事例と運営ノウハウ
10-1. 一風堂・ラーメン山岡家などの展開戦略
フランチャイズの世界で成功を収めた代表格が「一風堂」や「ラーメン山岡家」です。両者は異なるアプローチでフランチャイズ展開を進めてきましたが、それぞれの戦略には学ぶべきポイントがあります。
「一風堂」は、味とブランディングを極限まで磨き上げたうえで、海外展開も積極的に行うグローバル志向のブランド。直営店で徹底的にモデルを検証した後、条件を満たしたパートナーのみをフランチャイズとして採用する選別型方式を採用しています。
一方で「ラーメン山岡家」は、地方中心に着実に出店し、ロードサイド店舗での高回転モデルを確立。全国展開を視野に入れつつ、ドライバー層・夜間帯利用など独自の客層を開拓しながら成長してきました。
両者に共通するのは、商品の魅力とオペレーションの確立、そしてブランドの将来性を意識した慎重なFC展開です。
10-2. 成功企業のマネジメント術に学ぶ
成功したフランチャイズ本部には、明確なマネジメントポリシーと“再現性のあるオペレーション”があります。
たとえば「一蘭」は、店舗オペレーションの個別性を徹底的に排除し、誰が運営しても同じ味と接客が提供されるよう細かいマニュアルが設計されています。また、「ラーメン魁力屋」では、店舗スタッフのキャリア制度や表彰制度を整え、現場のモチベーション維持に注力しています。
このような施策が、フランチャイズオーナーだけでなく、従業員のエンゲージメントを高め、離職率低下・サービス品質の維持に寄与しているのです。
こちらで成功フランチャイズ事例に基づいたマネジメントノウハウを紹介しています。
—
11. フランチャイズ立ち上げを支援するコンサルの活用法
11-1. コンサルに依頼できること・できないこと
フランチャイズ本部を立ち上げる際、多くの事業者が「コンサル会社」を利用しています。これは、自社のノウハウだけでは対応しきれない法務・マニュアル整備・収支シミュレーションなど、専門的な支援を受けるためです。
たとえば「フランチャイズビジネス支援センター」や「フランチャイズアドバンテージ」などは、業種特化型のコンサルティングも行っており、ラーメン業態に特化した支援事例も豊富にあります。
ただし、コンサルは「立ち上げの土台を支える」役割にとどまり、最終的な意思決定やブランドのビジョン設計は、あくまでも本部側が担うべきです。
つまり、コンサルは「伴走者」であって「操縦者」ではありません。任せすぎると、事業の核がブレる恐れがあるため、適切な距離感を持った依頼が大切です。
11-2. コンサル選びのポイントと契約の注意点
良いコンサルタントを選ぶためのポイントは以下の通りです:
– ラーメン業界・飲食業界での実績があるか
– フランチャイズ立ち上げの事例を具体的に提示できるか
– 本部構築後もサポートが継続される体制か
– 契約内容が明確で、成果物や納期が文書で定められているか
また、コンサル契約では成果物の内容・納品期限・費用体系を明確にし、「丸投げにならない」「アドバイスのみで終わらない」関係性を築くことが重要です。
こちらでは、コンサル契約時に注意すべき具体的なポイントをまとめています。
—
12. フランチャイズに向くラーメン業態の条件とは?
12-1. スープの安定性・仕込み工数・店舗サイズの目安
フランチャイズ化を成功させるには、まず業態の「再現性」が非常に重要です。ラーメン業態において再現性の鍵を握るのが、“スープの安定性”と“仕込みのシンプルさ”です。
たとえば、「丸源ラーメン」では、セントラルキッチンによるスープの一括製造を導入することで、全国どこでも同じ味を再現しています。この手法により、調理経験のないオーナーでも味のばらつきがなく、店舗運営に集中できるのです。
また、仕込み時間や調理フローが複雑すぎる業態は、加盟店の再現が困難となり、教育コスト・オペレーション負担が高まります。小スペースで運営できる店づくりや、パートスタッフでも回せる調理システムの構築が理想です。
12-2. セントラルキッチン導入の是非と判断基準
セントラルキッチン(中央厨房)の導入は、ラーメンフランチャイズにおける品質安定の有効手段ですが、導入にはコストがかかります。そのため、小規模本部や立ち上げ初期には、外部業者への委託という選択肢も有効です。
「幸楽苑」は、早期からセントラルキッチンを活用し、複数業態を同一ラインで生産できるシステムを構築。これにより人件費・仕入れコスト・味の再現性という三点を高次元で実現しています。
こちらで、ラーメンフランチャイズに向いた業態の具体例を詳しく紹介しています。
—
13. 自社の直営店とフランチャイズの併用戦略
13-1. 直営とFCのバランスをとる展開手法
フランチャイズ展開を進める際に重要なのが、「直営店とFC店の適切なバランス」です。両者を併用することで、ブランドコントロールと資金効率の両立が可能になります。
直営店は、マニュアル検証や新メニューの実験場として活用できます。一方、FC店は資本をかけずに店舗数を拡大できるメリットがあります。たとえば「天下一品」は、全国に直営とFCのハイブリッド展開を行っており、本部がブランドの方向性をコントロールしながらも、オーナーの裁量を尊重しています。
また、直営店を一定数維持することで「オペレーションの最新データ」が本部に蓄積され、加盟者への教育やマニュアル改善にも反映できます。
13-2. ブランド力維持と運営体制強化のポイント
併用戦略において最も注意すべきは、“ブランド統一感”の維持です。直営店とFC店で味や接客レベルに差があると、消費者からの信用を失いかねません。
そのため、定期的な品質チェック、SV(スーパーバイザー)による巡回制度、全体研修などを通じて、全国どこでも同じブランド体験を提供できる仕組みが必要です。
「一蘭」では直営主義を基本としつつ、地域特化のパートナー展開を進めており、その際も品質のブレを最小限に抑える研修制度とチェック体制が徹底されています。
こちらで、直営・FC併用戦略の成功事例について解説しています。
—
14. 地方から始めるフランチャイズ立ち上げの可能性
14-1. 地方拠点を強みにしたFC化のステップ
近年は、東京や大阪といった大都市圏に限定せず、地方発で成功するラーメンフランチャイズも増えてきました。地域に根ざした味・サービス・価格帯が評価され、他地域への展開ニーズが生まれるパターンです。
たとえば、「ラーメン山岡家」は北海道発祥のブランドで、関東以北を中心に着実に多店舗展開を実現しました。また、九州地方では「一蘭」や「一風堂」など、地場ラーメン文化を背景に強いブランド力を築いた成功例が多数存在します。
地方から始める場合の最大の強みは「競合が少なく固定客がつきやすい」「原材料・人件費などの固定費が抑えやすい」といった地理的利点です。
14-2. 地元密着型ブランドの成功条件とは?
地元で根付いたブランドがフランチャイズ化に成功するには、以下のような条件が重要です:
– 地域ニーズを熟知し、価格・味・サービスに反映できている
– 地元メディア・口コミなどを通じた圧倒的認知がある
– 他地域への“持ち込みやすさ”(パッケージ化)が確立している
たとえば、富山の「富山ブラックラーメン」を全国に広げた「西町大喜」は、ご当地ラーメンの特異性を維持しながら、関東・関西へと出店範囲を広げています。
こちらでは、地方発フランチャイズの立ち上げポイントを詳しく紹介しています。
—
15. フランチャイズ立ち上げ後の運営体制と成長戦略
15-1. 継続的支援・契約更新・トラブル対応フロー
フランチャイズは「立ち上げて終わり」ではなく、「運営してからが本番」です。持続可能なモデルにするには、以下のような仕組みが必須です:
– 加盟者に対する定期的な研修・勉強会
– 店舗ごとの売上分析と改善提案の仕組み
– 契約更新時の評価制度と条件明示
– トラブル発生時の即時対応フロー(窓口・SV派遣)
「ラーメン魁力屋」では、開業後のサポート体制が特に手厚く、専任SVによる巡回、販促支援、食材の安定供給などが整備されており、加盟店の安心感が非常に高いと評価されています。
また、契約更新時に“改善点フィードバック”を行うことで、加盟者のモチベーション維持やクオリティ強化につながります。脱退防止にも非常に有効です。
15-2. 将来的な多店舗展開・M&A・事業譲渡の展望
フランチャイズ本部としての次なる成長戦略には、以下のような道があります:
– 加盟店舗数の段階的拡大(多店舗展開)
– 他社との連携や買収によるスケールアップ(M&A)
– 後継者不足対策としての事業譲渡制度の整備
「一風堂」などは、M&Aや海外進出も視野に入れたグローバル戦略を採用しており、そのための資本政策・人材戦略をあらかじめ整備しています。
また近年では、オーナー高齢化を背景に「事業承継フランチャイズ」も注目されています。店舗譲渡制度を明文化することで、新たな脱サラ志望者や独立希望者にとっても魅力的な制度となり得ます。
こちらでは、フランチャイズ展開後の成長戦略の具体例を紹介しています。
—