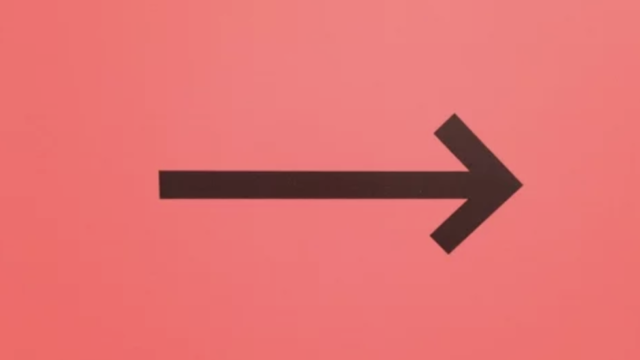—
1. フランチャイズとチェーン店の違いとは?潰れるリスクに関係あり
1-1. フランチャイズ店と直営チェーンの構造的な違い
フランチャイズとチェーン店、一見似たように見えるこの2つのビジネスモデルですが、その根本的な違いを理解することは非常に重要です。特に「潰れるリスク」の観点で見た場合、この違いが経営判断に大きな影響を及ぼします。
まず、**フランチャイズ店**は、個人または法人が「加盟」という形で本部と契約を結び、ブランドやノウハウを借りる形で店舗を運営します。一方、**チェーン店**は基本的に本部がすべてを所有・運営する「直営店」です。
この違いが意味するのは、**フランチャイズはオーナーに経営の責任があり、チェーン店では本部が責任を持つ**という点。つまり、フランチャイズでは本部の支援が不十分だったり、自身の経営能力が不足していると、潰れるリスクが一気に高まるのです。
1-2. 「潰れる」責任は誰にあるのか?経営主体の違い
フランチャイズ店が潰れた場合、その責任の多くはオーナーにあります。もちろん、ブランドの集客力が弱かったり、サポート体制が不十分な本部側にも非はありますが、契約上は「自己責任」とされるケースが一般的です。
一方、チェーン店が閉店する場合、その経営判断は本部が行うため、スタッフの雇用や顧客対応も本部主導で対応されます。つまり、**オーナー個人の負担が段違い**なのです。
こちらで、チェーンとフランチャイズの仕組みの違いを詳しく解説しています。
—
2. ラーメンフランチャイズが潰れる主な理由とは
2-1. 立地選び・人材不足・資金繰りの3大要因
ラーメンフランチャイズが潰れる大きな理由の一つが「立地の失敗」です。飲食業全般に言えることですが、集客力のある立地はすでに競合がひしめいており、後発で参入すると価格や味の勝負で苦戦しやすくなります。
次に「人材不足」。ラーメン店は長時間営業かつピークタイムの負荷が高く、経験者が少ない地域ではアルバイトの定着率が低くなります。オーナーが調理や接客に追われ、経営戦略まで手が回らずに失速するケースも少なくありません。
最後に「資金繰り」。多くのフランチャイズ本部では、毎月ロイヤリティを徴収する仕組みがありますが、売上が思うように伸びなければ、運転資金がすぐに底をついてしまいます。
2-2. FC本部の指導力と情報格差の落とし穴
また、フランチャイズ本部側の力量も潰れるかどうかに直結します。立ち上げ直後の本部や、サポート体制が弱いブランドでは、「言われた通りにやっても結果が出ない」事態が頻発します。
その原因のひとつが、「本部の情報と現場の情報のズレ」。たとえば、都市部でうまくいったモデルをそのまま地方に持ち込んでも、購買層が異なれば通用しません。にもかかわらず、それに気づかず本部マニュアル通りの運営を強制されて失敗に陥る例もあります。
こちらで、飲食FCの注意点を事前に確認しておきましょう。
—
—
3. 潰れたラーメンフランチャイズの実例一覧
3-1. 過去に撤退した有名ラーメンFCの実態
ラーメンフランチャイズの世界にも、かつては脚光を浴びながらも、撤退に追い込まれたブランドがいくつもあります。代表的な例として挙げられるのが「麺屋武蔵」のフランチャイズ化の失敗です。東京を中心に人気を誇っていた同ブランドですが、地方へのFC展開において味の再現性やスタッフ教育の難しさ、地域ごとの食文化の壁に直面。結果的に複数店舗が閉店に追い込まれました。
また、「どさん子ラーメン」も全国展開していた時期がありますが、急速拡大の反動で本部サポートが行き届かず、オーナーとの軋轢やクレームが続出。長年愛されていた老舗ブランドでも、**本部と加盟店の関係性がうまく機能しなければ撤退を招く**という教訓を残しました。
3-2. SNSや口コミに見る“閉店の理由”とは
現在では、X(旧Twitter)やGoogleクチコミなどのSNSでリアルな声が拾える時代です。例えば「開業後半年で閉店した」「サポートが全然なくて困った」「結局自分一人で全部やる羽目になった」などの投稿は、検討段階にある人にとって重要な判断材料になります。
実際、ある加盟者は「○○ラーメンFCに参加したが、サポートと聞いていた内容と違い、開業準備も営業も一人でこなす羽目になった」とブログで綴っています。表向きのPRだけでなく、こうしたリアルな声を拾うことが、**潰れるリスクを事前に防ぐ第一歩**です。
こちらで、失敗事例と対策をあらかじめ確認しておきましょう。
—
4. フランチャイズ加盟店の撤退率とその実情
4-1. 飲食業界全体とラーメンFCの平均撤退率
中小企業庁のデータや各種調査によると、飲食業界全体における**1年以内の撤退率は約30%、3年以内で約50%**とも言われています。これに対し、ラーメンフランチャイズは比較的認知度が高いジャンルでありながら、開業資金の高さと人手不足の影響により、撤退率は他の飲食業種より高めです。
特に、1日あたりの回転数が落ちる郊外立地では、**固定費に対して売上が追いつかず赤字が続きやすい**ため、早期撤退を余儀なくされるケースが後を絶ちません。
4-2. 高撤退率ブランドに共通する特徴とは
撤退率が高いフランチャイズブランドにはいくつか共通点があります。まず、「出店基準が甘い」「エリア調査が不十分」「本部の実績が浅い」などのケースが目立ちます。言い換えると、**急拡大を狙って無理な加盟を勧める本部**は注意が必要です。
また、ロイヤリティの設定が売上に連動せず**固定費で徴収されるモデル**は、赤字でも支払いが発生し、撤退を早める要因になりがちです。事前に本部の過去5年間の出店数と撤退数を確認し、「数字で信用できるか」を見極めましょう。
こちらで、加盟前に確認すべき撤退リスクの項目をチェック!
—
5. フランチャイズ店が潰れたらどうなる?
5-1. 契約解除と違約金の流れを把握しよう
フランチャイズ契約を途中で解約する場合、多くのケースで**違約金や原状回復費用**が発生します。たとえば「最低契約年数5年」に満たずに撤退した場合、残存期間分のロイヤリティ支払いを求められることもあります。
さらに、契約内容によっては**仕入れ義務や設備買取条件**など、事業終了後も継続して支払いが発生する条項が含まれていることがあるため、契約書の内容を事前に精査することが極めて重要です。
5-2. 設備・在庫・従業員への影響とその処理
店舗を閉める際には、厨房機器や客席設備の処分・譲渡、在庫品の返品や廃棄、そして従業員の雇用調整など、想像以上に多くの手続きが必要になります。
また、社員やアルバイトを突然解雇すれば、トラブルに発展するリスクもあります。撤退を決断する場合は、**本部だけでなく社会保険労務士や行政書士などの専門家に相談しながら進めることが望ましい**です。
こちらで、閉店対応時の手続き例を学べます。
—
—
6. フランチャイズ撤退にかかるコストとリスク
6-1. 原状回復・契約解除料・債務精算の実態
フランチャイズ経営において、撤退は最後の選択肢ですが、実際に撤退を決断した場合には多くのコストが伴います。まず最も多いのが「原状回復費用」。飲食店、特にラーメン屋は厨房設備や排気ダクトなど特殊な設備が多く、撤去だけで**数十万〜百万円以上**かかるケースがあります。
さらに、契約途中での撤退には「違約金」が発生する場合もあります。たとえば、**フランチャイズ契約が5年で残り2年を残して撤退**する場合、「2年分のロイヤリティや営業保証金の返還不可」などが記載されていることも。
また、月額費用の未払い、リース残債、業者への未払い費用などを合わせると、撤退時に**200〜500万円規模の清算費用**が必要になる例も珍しくありません。
6-2. 想定外の“経済的ショック”を防ぐには
このような撤退に伴う経済的ダメージを避けるためには、開業前から「最悪のシナリオ」を想定した備えが不可欠です。契約前に**解約条項を弁護士にチェックしてもらう**、撤退時の費用を逆算して資金に余裕を持っておく、といった工夫が後悔を防ぎます。
さらに、撤退後の再起を視野に入れ、**設備を中古販売できるルートを確保**しておいたり、金融機関との信頼関係を崩さないよう支払い計画を立てるなど、長期的な視点も重要です。
こちらで、撤退時のコスト対策を事前に確認しましょう。
—
7. 撤退する時の正しい手続きと進め方
7-1. 本部への連絡〜契約解除までのステップ
フランチャイズ店を閉じる場合、最初に行うべきは「本部への正式な連絡」です。感情的に閉店を決めて一方的に辞めるのはNG。契約書に記載されている「解約通告期限(例:3ヶ月前通知)」を守り、書面で通知する必要があります。
その後、本部担当者と面談し、撤退理由や店舗の今後(売却か閉鎖か)について協議します。場合によっては、後継オーナーを紹介してもらえる「事業譲渡」という形でスムーズに契約解除が進むこともあります。
7-2. 弁護士や専門家への相談タイミング
問題は、契約内容に不明点があったり、本部と意見が合わない場合です。このようなときは、早めに弁護士に相談するのがベストです。**フランチャイズ専門の弁護士**なら、トラブルの予防や交渉も代行してくれます。
また、原状回復や人件費精算などが絡む場合は、社会保険労務士や税理士などの専門家とチームを組んで「損をしない撤退」を目指すのが成功の鍵です。
こちらで、撤退手続きの基本フローをチェック!
—
8. フランチャイズ本部が倒産したら加盟店は?
8-1. ライセンス消失や供給ストップのリスク
フランチャイズ本部自体が倒産するケースも決して珍しくありません。この場合、加盟店が被る影響は非常に大きくなります。まず、ブランドの使用権(商標ライセンス)が失われ、**看板や商品名を使い続けられなくなる**リスクが生じます。
さらに、本部が仕入れを一括管理している場合、**スープ・麺などの専用食材の供給が止まり、営業そのものが不可能に**なるケースも。依存度が高いほど、損害が大きくなる傾向にあります。
8-2. 独立継続するか撤退するかの判断基準
こうした事態に備えて、多くのオーナーが「自力継続」か「撤退」の選択を迫られます。ブランド名は使えなくとも、自身のオリジナルラーメンで独立継続するケースもあれば、仕入れや販促が一切できなくなって撤退せざるを得ないケースも。
特に「スープが本部製造専用」「設備がリース」など、**本部依存型のフランチャイズほどリスクが高くなる**ため、契約時点で依存度の低い構成を選ぶことがポイントです。
こちらで、フランチャイズ本部倒産時の対応方法を学びましょう。
—
9. 潰れないための事前チェックリスト
9-1. 加盟前に見るべき本部の健全性
フランチャイズで潰れないために最も重要なのが「加盟前の見極め」です。まずは、本部の財務情報・直営店の業績・撤退率・他加盟者の声などをしっかり調べましょう。
特に注意したいのが「直営店が少ない本部」。これは実績がなく、加盟金で収益を上げている“危ない”本部である可能性があるためです。**直営店数3店舗未満+売上非公開の本部は要警戒**とされています。
9-2. 契約書の“撤退関連項目”を読み解こう
契約書には、「中途解約の条件」「ロイヤリティ清算」「設備の取り扱い」など、撤退時に直結する内容が多く記載されています。素人目にはわかりにくいため、契約前には必ず**フランチャイズ契約に強い弁護士**にチェックしてもらうことを強くおすすめします。
また、開業前に複数のフランチャイズを比較して、「サポートの厚み」「撤退率」「収益性」を総合的に評価することで、潰れにくいモデルを選ぶことができます。
こちらで、契約時の確認ポイントをチェック!
—
10. フランチャイズでよくある失敗と回避方法
10-1. 自己資金不足・安易な加盟のリスク
「自己資金が少なくてもOK」と言われてフランチャイズに加盟したものの、実際には開業後に追加費用がかさみ、資金ショートに陥る例は後を絶ちません。特に、厨房設備や広告費など、**開業後にかかる“隠れコスト”**を見落とす人が多いのです。
また、「儲かりそうだから」と安易に飛びついた結果、業種との相性が合わず早期撤退する人もいます。**自分の性格やライフスタイルに合った業態かをしっかり見極める**必要があります。
10-2. 初心者が見落としがちな落とし穴
未経験者がやりがちなミスの一つに、「現場を他人に任せきりにする」ことがあります。ラーメン屋のように人の出入りが激しい業界では、オーナーが現場に関心を持たないと**品質や接客が崩れやすくなり、結果的に客足が遠のく**原因になります。
成功しているオーナーの多くは、厨房にも立ち、現場を把握した上で経営判断をしています。加盟後も「現場感覚」を忘れずに持ち続けることが、失敗を回避する大きなポイントです。
こちらで、開業前後の注意点をまとめて確認しておきましょう。
—
—
11. 潰れたフランチャイズオーナーのその後
11-1. 借金・転職・再チャレンジの実例
フランチャイズ経営がうまくいかず撤退に追い込まれた場合、その後の人生にどのような影響が出るのでしょうか?実際、ラーメンフランチャイズを閉店したあるオーナーは、開業資金として借りた約1000万円のうち500万円を返済しきれず、**個人保証付きで借り入れたため自己破産を検討**せざるを得ない状況に追い込まれました。
また、フランチャイズ撤退後に飲食業界を離れてサラリーマンに戻ったという人もいます。「開業時に夢を見すぎてしまった」「契約内容をきちんと理解していなかった」と後悔する声も多く見られます。
一方で、撤退後に経験を糧にして別のフランチャイズに再チャレンジし、成功を収めたケースもあります。たとえば「壱角家」や「どうとんぼり神座」など、**本部のサポートが手厚く撤退率が低いフランチャイズに改めて加盟し、リベンジを果たした事例**も存在します。
11-2. 再起のために活用できる支援制度
フランチャイズ撤退後の再出発を支える公的制度もあります。日本政策金融公庫の「再チャレンジ支援融資」や、厚生労働省の「再就職支援セミナー」「生活再建支援金」などを活用すれば、精神的・経済的な立て直しが可能です。
また、廃業経験者向けにメンタリングやビジネス再構築の支援を行っているNPOや地方自治体もあるため、**早めに情報収集し、自分だけで抱え込まないことが重要**です。
こちらで、フランチャイズ再出発に役立つ事例も確認できます。
—
12. 潰れる前に兆候を見抜くために
12-1. 売上低下・本部支援の変化に注目
撤退という最悪の事態に至る前に、いかにして兆候を見抜くかは非常に重要です。まず注目すべきは「売上の変化」。1日平均の客数が1週間以上連続して下がる、週末の来店数が急減するなど、**明確な売上低下は“赤信号”**です。
また、本部のサポート体制が以前に比べて疎かになってきたと感じる場合も注意が必要です。「担当者が変わった後、連絡が取りにくくなった」「マニュアルの更新が止まった」などの変化は、本部の経営状況が厳しい兆しでもあります。
12-2. 店舗運営の“違和感”を見逃さない
オーナー自身が感じる「違和感」も見逃してはいけません。「最近スタッフの士気が下がっている」「原材料の価格が急に上がった」「SNSで悪評が増えている」など、**現場の小さなサインがやがて経営悪化の大きな波になる**可能性があります。
売上だけでなく、スタッフの離職率やクレーム件数なども経営のバロメーター。日々の運営の中で“なんとなくおかしい”と感じたら、その違和感を放置せず、すぐに原因を突き止める姿勢が大切です。
こちらで、フランチャイズリスクの見極め方法を学んでおきましょう。
—
—
13. 潰れやすいフランチャイズの見抜き方
13-1. 高額ロイヤリティ・サポート不足の注意点
「開業後にすぐ閉店してしまう」――そんなフランチャイズには明確な共通点があります。最も典型的なのが、**ロイヤリティが高すぎるにも関わらず、サポートが薄いフランチャイズ**です。たとえば、月売上の15%以上をロイヤリティで持っていかれる上に、SV(スーパーバイザー)がほとんど来ない、研修も2〜3日程度しかない、といったパターンです。
実際に一部のラーメンチェーンでは、「加盟金300万円+ロイヤリティ10%」という高コスト構造ながらも、本部が運営ノウハウをまともに教えてくれず、**1年以内に3割の店舗が撤退**したという報道もありました。
こうした情報は契約書だけではわかりません。**既存オーナーの声や評判、SNSでの実体験の発信**を調査し、本部が本当に信頼できるかを慎重に見極める必要があります。
13-2. 本部の財務・実績・運営体制の確認法
潰れやすいフランチャイズを見抜くもう一つの方法は、**本部の財務や直営店の実績、運営体制**を冷静に調べることです。たとえば、直営店がゼロで「加盟金ビジネス」に依存している本部は非常に危険です。
また、決算書が非公開だったり、赤字が続いている企業、幹部が頻繁に入れ替わる企業も注意が必要です。公開企業や商工リサーチの情報、行政処分歴などをチェックすることで、ある程度の「健全性」は見えてきます。
こちらで、フランチャイズ本部の見極めポイントを事前に確認しておきましょう。
—
14. 撤退後の生活設計と収入回復戦略
14-1. 雇用・再チャレンジ・転業の道筋
フランチャイズ経営から撤退した後、生活をどう立て直すかは大きな課題です。まず、借金や資金繰りが重荷になっている場合、**債務整理や任意整理、リスケジュール(返済猶予)**といった法的手段も検討に入れるべきです。
その上で、再就職を目指すなら、飲食業のマネジメント経験を活かして「店舗マネージャー」や「SV職」への転職が現実的です。また、クラウドワークスなどを通じて業務委託やフリーランスとして活動するという道もあります。
一方、再度フランチャイズにチャレンジしたい場合は、**撤退率の低いブランド**や初期費用の少ないモデル、または「ロイヤリティ0円」のタイプから再スタートするのも有効です。
14-2. 心の立て直しと家族との向き合い方
撤退は経済的な問題だけでなく、**精神的にも大きな打撃**を与えるものです。家族の理解を得られなかった、生活が不安定になった、という悩みを抱える人は少なくありません。
だからこそ、再起に向けては「心の回復」が大前提になります。NPOや自治体が開催しているメンタルケアのカウンセリングや、同じ境遇の人との交流会に参加するなど、**一人で抱え込まないこと**が大切です。
こちらで、フランチャイズからの再起についての考え方を参考にしてみてください。
—
15. 「潰れないフランチャイズ選び」が最大の予防策
15-1. 撤退率が低い安心ブランドの特徴
「潰れないための最大の防御策」は、言うまでもなく**最初のフランチャイズ選びを間違えないこと**です。では、どんなブランドが潰れにくいのか?答えは、「直営店が安定して黒字を出している」「ロイヤリティが売上連動ではなく、定額制」「開業後の研修・SVサポートが充実している」ブランドです。
たとえば、「横浜家系ラーメン壱角家」は、**研修制度の充実度や仕入れの安定性、集客支援体制**に定評があり、フランチャイズ初心者にも人気の高いブランドのひとつです。
また、「チキン南蛮専門店 からやま」や「来来亭」なども撤退率が極めて低く、ブランドへの信頼感が高い点が共通しています。
15-2. 将来性・サポート体制を軸に考える加盟判断
最終的な判断軸として重要なのは、「今稼げるか」だけでなく「将来的にも稼ぎ続けられるか」。つまり、**フランチャイズの“持続可能性”と“市場性”を見極める**ことが重要です。
契約年数が長い場合、社会や経済の変化にも強いフランチャイズを選ぶ必要があります。また、**コロナ禍など非常時にも対応できるテイクアウト対応・デジタル集客の有無**などもチェックポイントです。
加盟希望者は、数字だけでなく“本部の姿勢”や“現場の雰囲気”を五感で感じたうえで判断することが、潰れない経営のスタートラインになります。
こちらで、フランチャイズ選びのコツを確認しておきましょう。
—